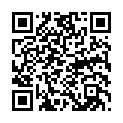全国自動車交通労働組合連合会はハイタク産業に従事する労働者で構成する労働組合の連合体です。本ホームページは、どなたでも自由に全てご覧いただけます。
ホーム
>
ニュース
> 2022年4月4日掲載
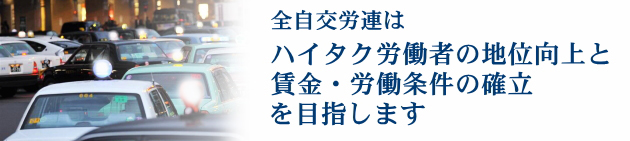

苦しい生活からの脱却を願う全国ハイタク労働者の叫びが、東京・永田町にこだましました。
全自交労連、交通労連ハイタク部会、私鉄総連ハイタク協議会で構成するハイタクフォーラム(代表=溝上泰央全自交労連中央執行委員長)は3月10日、東京・永田町の星稜会館で「適正な運賃・料金を求める総決起集会22春闘勝利!ライドシェア反対!」を開催。全国から167人の仲間が集結し、コロナ禍を乗り越え、賃金・労働条件を改善するためには運賃改定が必要と声を揃えました。連合の清水秀行事務局長をはじめとする15人の来賓からも連帯が表明されています。9日に厚生労働省・国土交通省への要請行動、10 日の集会後には、タクシー政策議員連盟との意見交換も実施。ハイタク労働者の苦境を訴え、改善を求めました。
集会で、主催者を代表してあいさつした溝上代表は、ハイタク労働者が果たしてきた社会的役割の大きさと、それに見合わない劣悪な賃金・労働条件に対して怒りの声を上げ、「まさにいま、闘われている春闘は、この待遇を変えるための重要な場。全国のハイタク労働者が、あきらめずに会社と交渉を続け、どんな形でも、賃金・労働条件の向上を勝ち取りましょう」と強く呼び掛けました。
そして賃金・労働条件の向上には「設備費や燃料費の高騰に見合った運賃改定が必須だ」と強調し、「すべての地域で、適正な人件費をまかなえるだけの運賃・料金を実現するため、全国のハイタク労働者の声を一つに合わせ、行政や事業者にぶつけていかなくてはなりません」と訴えました。
また溝上代表は「mobi(モビ)」や「nearMe(ニアミー)」など安さを売りにする新サービスについて「タクシー事業者がきちんと関わる形にしなければ、運賃改定を実施しても運送収入は上がらず、公共交通が破壊される」と厳しく批判。ライドシェア合法化を掲げる維新の会の勢力拡大を強く警戒し、参議院選挙での闘いの重要性を強調しました。
3月9日、ハイタクフォーラムは国土交通省への要請交渉を行いました。
24項目もの要請を提出(=写真)して、国交省の姿勢を問い、さらに13人が発言して現場の思いを伝えています。重要な回答と、全自交労連の出席者の発言を紹介します。交渉には立憲民主党の近藤昭一、小宮山泰子、城井崇各衆議院議員らも同席しました。

主な回答(要約)
◆ライドシェア
(大阪万博などでの〝期間限定〟も含め)「安全確保、利用者保護の観点から認めるわけにはいかない」
◆運賃改定
「労働条件改善につながらなければ、運賃改定の錦の御旗もかすむ。改定して終わりではなく、労働条件向上につながるよう、国交省としてしっかり事業者に言っていく」
◆格差是正
バスの運賃改定では全産業との賃金格差を埋める仕組みができたのに、なぜタクシーには導入しないのかという要望に対し、「タクシーは、歩合制、日勤や隔日勤務など多様な勤務実態など特有の事情が存在するので、全産業平均賃金と単純に比較して、適正な人件費を判断することは必ずしも適当ではない。一方で、運賃算定に当たり、人件費に一定割合を積み増す措置を取っている。運転者の賃金が十分に確保されるよう取り組むことが重要と考えている」
◆運転者負担と累進歩合
「配車アプリ手数料などを運転者に負担させることは、見直すよう業界に求めており、運輸局も通じて必要な指導を行いたい。累進歩合は厚労省と連携し、廃止に向けた働きかけを継続する」
◆乗務員への危険手当支給
「希望にそえず申し訳ない。今後の制度設計の参考にする」
◆定額乗り放題モビ
「実験ではなく、本格運行する場合は、各自治体の地域公共交通会議の承認が必要。地域公共交通会議がなければ、つくるしかない」
「既存のバス・タクシーの需要を損なうものでないか分析していくことが重要。実証実験の内容を注視していく」
◆脳MRI検査などの助成
「費用負担が大きな課題となっていることは理解しており、国として助成することも含めて検討中」
◆変動運賃(ダイナミックプライシング)
「昨年行った実証実験の結果を検証中。今後、有識者の検討会を設置する」
◆配車アプリでの、割引競争の弊害について
「利用者にとって利便性は高いが、公共交通機関のサービスとして不適切な内容になっていないか、動向を注視して、適切に対応したい」
◆特定地域「不同意」問題(下部記事にて紹介)
ハイタク乗務員の労働環境は、全産業の中でも非常に厳しい。持続可能とするためには、将来に希望を持てる労働環境が必須であり、皆さまと取り組みたい。ライドシェアを導入しない姿勢を貫き、連合としても政府に強く求めていきます。
昨年12月、乗合バスでは(全産業平均賃金との格差を解消するよう)運賃認可の処理方針が変わったが、タクシー産業においてもこういった制度を作っていくことが、今、一番大事な視点。交運労協60万人の思いを込めて取り組みたい。
ウクライナ侵略が起き、避難する方をタクシーが輸送している。地震の時もそうだが、電車やバスが止まってもタクシーは動き、その中心に運転者の方がおられることを忘れてはなりません。安全の確保や待遇の向上を応援していきます。

【出席者】
議連より小宮山泰子幹事長、森山浩行幹事長代行 全タク連より、武居利春副会長、神谷俊広理事長






国交省に対応要請
ハイタクフォーラムは3月9日に行った国土交通省との交渉で、「事業者の意向で不同意となる地域が多いことは特措法の目的に反している。所管行政として対策を」、「特定・準特定の指定基準の見直しを」といった要請を行いました。
国交省側は「特定地域については、新規参入や増車の禁止など特別の措置となるため、地域の関係者において十分に議論し、理解をえる必要がある」、「指定基準については、コロナ前、コロナ後で状況も違い、必要に応じて検討するタイミングがくれば、しっかり考えたい」と回答するにとどまり、具体的な改善策は示されませんでした。
これらの問題について、全自交新潟地連の海藤正彦書記長は「新潟交通圏では5社が営業制限に応じなかったが、運輸局は勧告も命令も出さないまま、ついに特定地域が解除されてしまった。本当に勧告・命令を出せるのか」とただしました。
また全自交北海道地連の鈴木久雄委員長は、適正車両数の基準について「札幌交通圏では46%、旭川交通圏では46・7%以上の供給削減が必要になる。(実際に)これだけの供給削減を行えば需要に応じられず、降雪時の配車は一層困難になり、雇用問題も発生する」と問題提起し、「指定基準の見直しは喫緊の課題だ」と国交省に求めています。
いま現実に、改正特措法の実効性が失われつつあり、協議会での議論すら行われない状況がある以上、まずは国交省が運用ルールを見直す以外に解決策はありません。同時に特措法の限界を乗り越えるため、タクシー事業法(仮称)の制定を求める運動を一層強化していく必要があります。

全自交労連は、ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻に断固として抗議し、即時・無条件の撤退を要求します。ウクライナの人々、そしてロシア国内を含め世界中で戦争反対の声を上げる人々への連帯を表明します。
核兵器による脅しや原発への攻撃も絶対に許容できません。国内でも核武装論者が勢いづいていますが、核の拡散が進めば、人類を含む全生物の絶滅リスクが跳ね上がることを忘れてはなりません。
なにより、この戦争が続くほど、物価は上がり生活は苦しくなります。ウクライナの人々のため、私たち自身の平和と生活を守るため、抗議の声を。「ロシアは撤退せよ!」。
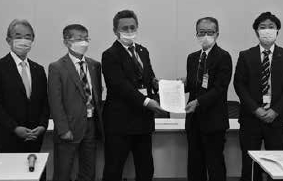



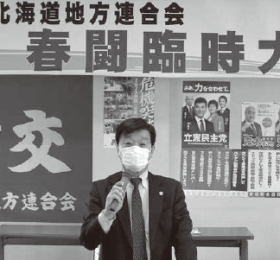


訂正
2月15日付1220号の2面に掲載した「春闘標語を初公募」の記事で、組合員の方のお名前が間違っておりました。「新しい資本主義の前に格差是正! 今こそ勝ち取れ2022春闘」の標語を考案されたのは林さんではなく、大和自交労組銀座支部の佐藤正三さんです。お詫びして訂正します。
このページの掲載記事
■ ハイタクフォーラム 総決起集会「全国で運賃改定を」
■ ウクライナに平和を!
■ 厚労省要請交渉
■ 青森地連中央委員会 春闘で生活賃金の確保!
■ 釜石市長に要請
■ 愛媛地本 月額1万円を要求の柱に
■ 北海道地連 春闘臨時大会
■ 富山地連第43回委員会
■ 岩手地本 活発に組織拡大
■ ハイタクフォーラム 総決起集会「全国で運賃改定を」
■ ウクライナに平和を!
■ 厚労省要請交渉
■ 青森地連中央委員会 春闘で生活賃金の確保!
■ 釜石市長に要請
■ 愛媛地本 月額1万円を要求の柱に
■ 北海道地連 春闘臨時大会
■ 富山地連第43回委員会
■ 岩手地本 活発に組織拡大
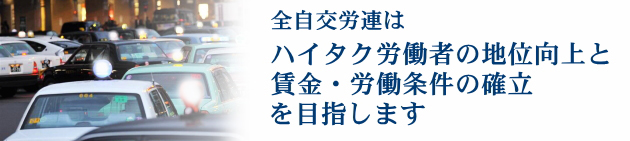
ハイタク労働者の苦境 議員や行政にも訴え

ハイタクフォーラム総決起集会。全国から3産別の仲間167人が集結。(3月10日、東京・星陵会館)
苦しい生活からの脱却を願う全国ハイタク労働者の叫びが、東京・永田町にこだましました。
全自交労連、交通労連ハイタク部会、私鉄総連ハイタク協議会で構成するハイタクフォーラム(代表=溝上泰央全自交労連中央執行委員長)は3月10日、東京・永田町の星稜会館で「適正な運賃・料金を求める総決起集会22春闘勝利!ライドシェア反対!」を開催。全国から167人の仲間が集結し、コロナ禍を乗り越え、賃金・労働条件を改善するためには運賃改定が必要と声を揃えました。連合の清水秀行事務局長をはじめとする15人の来賓からも連帯が表明されています。9日に厚生労働省・国土交通省への要請行動、10 日の集会後には、タクシー政策議員連盟との意見交換も実施。ハイタク労働者の苦境を訴え、改善を求めました。
集会で、主催者を代表してあいさつした溝上代表は、ハイタク労働者が果たしてきた社会的役割の大きさと、それに見合わない劣悪な賃金・労働条件に対して怒りの声を上げ、「まさにいま、闘われている春闘は、この待遇を変えるための重要な場。全国のハイタク労働者が、あきらめずに会社と交渉を続け、どんな形でも、賃金・労働条件の向上を勝ち取りましょう」と強く呼び掛けました。
そして賃金・労働条件の向上には「設備費や燃料費の高騰に見合った運賃改定が必須だ」と強調し、「すべての地域で、適正な人件費をまかなえるだけの運賃・料金を実現するため、全国のハイタク労働者の声を一つに合わせ、行政や事業者にぶつけていかなくてはなりません」と訴えました。
また溝上代表は「mobi(モビ)」や「nearMe(ニアミー)」など安さを売りにする新サービスについて「タクシー事業者がきちんと関わる形にしなければ、運賃改定を実施しても運送収入は上がらず、公共交通が破壊される」と厳しく批判。ライドシェア合法化を掲げる維新の会の勢力拡大を強く警戒し、参議院選挙での闘いの重要性を強調しました。
国交省交渉
エッセンシャルワーカーに直接の支援を
運賃改定の主題は賃金労働条件の改善
エッセンシャルワーカーに直接の支援を
運賃改定の主題は賃金労働条件の改善
3月9日、ハイタクフォーラムは国土交通省への要請交渉を行いました。
24項目もの要請を提出(=写真)して、国交省の姿勢を問い、さらに13人が発言して現場の思いを伝えています。重要な回答と、全自交労連の出席者の発言を紹介します。交渉には立憲民主党の近藤昭一、小宮山泰子、城井崇各衆議院議員らも同席しました。

冒頭、溝上泰央代表は「エッセンシャルワーカーであるハイタク労働者の生活はまさに風前の灯火。ハイタク産業が持続可能な移動サービスとして、利用者に安全・安心を提供できる環境の構築を」と求めました。
国土交通省自動車局旅客課の大辻統課長は、エッセンシャルワーカーとしてのハイタク労働者に敬意を表明。運賃改定について「適正なタイミングで改定されることが望ましい。審査が始まればすみやかに改定がなされるよう対応したい」と述べ、1リッター当たりの上限額が5円から25円に引き上げられたLPガス高騰支援についても早急に対応する考えを示しました。「タクシーの質を決めるのは運転者の皆さまだ」とし、安定して長く働ける環境構築に取り組む意欲も語りました。
全自交労連の出席者は次のような意見を国交省にぶつけています。
東京地連の菊池るみ副委員長は、雇用調整助成金は休業者への支援にすぎず「普通に働いている者がなんの支援も受けられない。これはおかしい」と指摘。エッセンシャルワーカーと認めている以上、「危険手当」など乗務員への直接支援を求めました。
富山地連・石橋剛委員長は、運賃改定が賃金・労働条件の改善に確実に反映されるよう、検証と事後のフォローを強く要求。また、UDタクシーの普及とともに、本来介護タクシーに乗車すべき介助の必要な乗客の輸送が増加し、歩合給の中で、労働者が賃金上の不利益をこうむっている状況を説明して、区分の明確化を要望しました。
北海道地連・鈴木久雄委員長は夜間実車時の行灯消灯が地域ごとに扱いが違うことを批判し、説明を求めました。
国土交通省自動車局旅客課の大辻統課長は、エッセンシャルワーカーとしてのハイタク労働者に敬意を表明。運賃改定について「適正なタイミングで改定されることが望ましい。審査が始まればすみやかに改定がなされるよう対応したい」と述べ、1リッター当たりの上限額が5円から25円に引き上げられたLPガス高騰支援についても早急に対応する考えを示しました。「タクシーの質を決めるのは運転者の皆さまだ」とし、安定して長く働ける環境構築に取り組む意欲も語りました。
全自交労連の出席者は次のような意見を国交省にぶつけています。
東京地連の菊池るみ副委員長は、雇用調整助成金は休業者への支援にすぎず「普通に働いている者がなんの支援も受けられない。これはおかしい」と指摘。エッセンシャルワーカーと認めている以上、「危険手当」など乗務員への直接支援を求めました。
富山地連・石橋剛委員長は、運賃改定が賃金・労働条件の改善に確実に反映されるよう、検証と事後のフォローを強く要求。また、UDタクシーの普及とともに、本来介護タクシーに乗車すべき介助の必要な乗客の輸送が増加し、歩合給の中で、労働者が賃金上の不利益をこうむっている状況を説明して、区分の明確化を要望しました。
北海道地連・鈴木久雄委員長は夜間実車時の行灯消灯が地域ごとに扱いが違うことを批判し、説明を求めました。
主な回答(要約)
◆ライドシェア
(大阪万博などでの〝期間限定〟も含め)「安全確保、利用者保護の観点から認めるわけにはいかない」
◆運賃改定
「労働条件改善につながらなければ、運賃改定の錦の御旗もかすむ。改定して終わりではなく、労働条件向上につながるよう、国交省としてしっかり事業者に言っていく」
◆格差是正
バスの運賃改定では全産業との賃金格差を埋める仕組みができたのに、なぜタクシーには導入しないのかという要望に対し、「タクシーは、歩合制、日勤や隔日勤務など多様な勤務実態など特有の事情が存在するので、全産業平均賃金と単純に比較して、適正な人件費を判断することは必ずしも適当ではない。一方で、運賃算定に当たり、人件費に一定割合を積み増す措置を取っている。運転者の賃金が十分に確保されるよう取り組むことが重要と考えている」
◆運転者負担と累進歩合
「配車アプリ手数料などを運転者に負担させることは、見直すよう業界に求めており、運輸局も通じて必要な指導を行いたい。累進歩合は厚労省と連携し、廃止に向けた働きかけを継続する」
◆乗務員への危険手当支給
「希望にそえず申し訳ない。今後の制度設計の参考にする」
◆定額乗り放題モビ
「実験ではなく、本格運行する場合は、各自治体の地域公共交通会議の承認が必要。地域公共交通会議がなければ、つくるしかない」
「既存のバス・タクシーの需要を損なうものでないか分析していくことが重要。実証実験の内容を注視していく」
◆脳MRI検査などの助成
「費用負担が大きな課題となっていることは理解しており、国として助成することも含めて検討中」
◆変動運賃(ダイナミックプライシング)
「昨年行った実証実験の結果を検証中。今後、有識者の検討会を設置する」
◆配車アプリでの、割引競争の弊害について
「利用者にとって利便性は高いが、公共交通機関のサービスとして不適切な内容になっていないか、動向を注視して、適切に対応したい」
◆特定地域「不同意」問題(下部記事にて紹介)
総決起集会 力強い連帯の声
ハイタク乗務員の労働環境は、全産業の中でも非常に厳しい。持続可能とするためには、将来に希望を持てる労働環境が必須であり、皆さまと取り組みたい。ライドシェアを導入しない姿勢を貫き、連合としても政府に強く求めていきます。
昨年12月、乗合バスでは(全産業平均賃金との格差を解消するよう)運賃認可の処理方針が変わったが、タクシー産業においてもこういった制度を作っていくことが、今、一番大事な視点。交運労協60万人の思いを込めて取り組みたい。
ウクライナ侵略が起き、避難する方をタクシーが輸送している。地震の時もそうだが、電車やバスが止まってもタクシーは動き、その中心に運転者の方がおられることを忘れてはなりません。安全の確保や待遇の向上を応援していきます。

【出席者】
議連より小宮山泰子幹事長、森山浩行幹事長代行 全タク連より、武居利春副会長、神谷俊広理事長

ハイタクフォーラム総決起集会では、総合司会を全自交・松永次央書記長、開会あいさつを交通労連ハイタク部会・小川敬二部会長、閉会あいさつを私鉄総連ハイタク協議会・志摩卓哉議長が担当。集会アピールを全自交東京地連の河西純誉さん(写真左)が提案し、前日の国交省・厚労省要請の概要報告を、全自交・野尻雅人書記次長、私鉄ハイタク・久松勇治事務局長が行いました。
ITF浦田部長 ライドシェア『変異株』に警戒
東北交運労協は12月11日、仙台市「ハーネル仙台」で第31回東北地方運輸行政懇談会を開き、東北交運労協からは加盟産別・地方組織の28名が出席。全自交東北地連から4名が出席しました。また、東北運輸局からは亀山局長をはじめ7名が出席し、コロナ禍における東北地方の交通・運輸の厳しい課題について意見交換しました。
東北交運労協の小池議長は挨拶で、コロナ禍の中での開催に感謝を述べるとともに、「迅速かつ徹底した新型コロナ感染症への対応を運輸局と連携して取り組んでいきたい」と述べました。
東北運輸局の亀山局長が日頃からの協力に感謝する挨拶をしたのに続き、運輸局の担当者が東北における運輸と観光の動向を報告し、要請事項に回答しました。
タクシー関係では、16項目の要請の中から、タクシー乗務員の感染防止について、「対策費用を引き続き支援していきたい」との回答がなされました。
意見交換では、全自交東北地連の江良委員長が運賃改定で公定幅運賃の幅が縮まったことを評価するとともに、このコロナ禍での厳しい現場の実態を訴え、協力を要請しました。さらに、タクシー事業者のほとんどが中小零細企業であるため、事業継続への支援協力についても要請しました。
東北運輸局からは「運輸局としても各支局長が自治体の首長を訪問し、タクシー・バスに対する交付金による支援を要請している」との答弁がありました。
東北交運労協の小池議長は挨拶で、コロナ禍の中での開催に感謝を述べるとともに、「迅速かつ徹底した新型コロナ感染症への対応を運輸局と連携して取り組んでいきたい」と述べました。
東北運輸局の亀山局長が日頃からの協力に感謝する挨拶をしたのに続き、運輸局の担当者が東北における運輸と観光の動向を報告し、要請事項に回答しました。
タクシー関係では、16項目の要請の中から、タクシー乗務員の感染防止について、「対策費用を引き続き支援していきたい」との回答がなされました。
意見交換では、全自交東北地連の江良委員長が運賃改定で公定幅運賃の幅が縮まったことを評価するとともに、このコロナ禍での厳しい現場の実態を訴え、協力を要請しました。さらに、タクシー事業者のほとんどが中小零細企業であるため、事業継続への支援協力についても要請しました。
東北運輸局からは「運輸局としても各支局長が自治体の首長を訪問し、タクシー・バスに対する交付金による支援を要請している」との答弁がありました。

タクシー政策議連と意見交換

近藤会長ら、議連メンバーが真剣にハイタク労働者の声を聞きました

愛知・本田委員長
ハイタクフォーラムは3月10日、衆議院第二議員会館でタクシー政策議員連盟に所属する国会議員と意見交換を実施。議連からは、国会審議の合間をぬって衆議院19人、参議院10人の国会議員が参加し、全国の労働者の切実な訴えに耳を傾けました。
議連の近藤昭一会長は「皆さんのお仕事は重要なインフラであり、皆さんをしっかり守っていくことがわれわれの役割です」と力強く表明し、森屋隆事務局長も「交通運輸労働者の安定した労働条件と職場を確保することが何よりも必要」と述べました。エッセンシャルワーカーへの支援について、小宮山泰子幹事長は「定義を明確にし、きちんと支えられる制度を目指したい」と語り、森山浩行幹事長代行は「内閣委員会筆頭理事として政府全体での定義や予算を議論したい」と前向きな姿勢を示しました。
意見交換の中で、全自交愛知地連の本田有委員長は、政府の賃上げ政策(法人減税)は、元々利益率が低く、コロナで大半が赤字のタクシー業界には「まったく合っていない」と指摘。検討されているトリガー条項解除についても「LPガスにかかる石油・ガス税は減税にならない」と述べ、タクシーにも配慮した政策の取り組みを要望。最後に「バスが撤退した地域でタクシーも撤退すればどうなるか想像して下さい。高知県須崎市では、商工会議所が中心となって地域のタクシーを残しましたが、これは本来は政治の仕事。地域公共交通としてのタクシー向けの施策をぜひお願いします」と訴えました。
議連の近藤昭一会長は「皆さんのお仕事は重要なインフラであり、皆さんをしっかり守っていくことがわれわれの役割です」と力強く表明し、森屋隆事務局長も「交通運輸労働者の安定した労働条件と職場を確保することが何よりも必要」と述べました。エッセンシャルワーカーへの支援について、小宮山泰子幹事長は「定義を明確にし、きちんと支えられる制度を目指したい」と語り、森山浩行幹事長代行は「内閣委員会筆頭理事として政府全体での定義や予算を議論したい」と前向きな姿勢を示しました。
意見交換の中で、全自交愛知地連の本田有委員長は、政府の賃上げ政策(法人減税)は、元々利益率が低く、コロナで大半が赤字のタクシー業界には「まったく合っていない」と指摘。検討されているトリガー条項解除についても「LPガスにかかる石油・ガス税は減税にならない」と述べ、タクシーにも配慮した政策の取り組みを要望。最後に「バスが撤退した地域でタクシーも撤退すればどうなるか想像して下さい。高知県須崎市では、商工会議所が中心となって地域のタクシーを残しましたが、これは本来は政治の仕事。地域公共交通としてのタクシー向けの施策をぜひお願いします」と訴えました。

北海道・鈴木委員長
また、全自交北海道地連の鈴木久雄委員長が「今年の大雪では、緊急時に必要で、お年寄りの足となるタクシーが走れなくなることもあった。雪の多い地域について、国としての対策を」と求めた事に対し、北海道選出の立憲民主党・徳永エリ参議院議員は「札幌ではタクシーが何台もスタックして、私も1台押させて頂きましたが、あれではとても仕事にならない。ましてや高齢化でどれだけ大変か」と理解を示し、「与野党の範囲を超えて取り組みたい」と答えました
全自交東京地連の沢頭満則執行委員は「タクシーの平均基準賃金を決めることはできないか」と提案。立憲民主党・末松義規衆議院議員は「国費を投入して中小企業を支援しながら、最低賃金を1500円まで上げる取り組みを立憲民主党でしている」と説明しました。
ほかにも、緊急小口資金などの借入金の返済猶予を求める声が上がりました。
全自交東京地連の沢頭満則執行委員は「タクシーの平均基準賃金を決めることはできないか」と提案。立憲民主党・末松義規衆議院議員は「国費を投入して中小企業を支援しながら、最低賃金を1500円まで上げる取り組みを立憲民主党でしている」と説明しました。
ほかにも、緊急小口資金などの借入金の返済猶予を求める声が上がりました。
特定地域指定 相次ぐ「書面のみ」不同意 踏みにじられる改正タク特措法
タクシー特定地域の指定基準を満たしながら、指定に「不同意」とする決定が全国で相次ぎ、基準を満たした38候補地の全てが「不同意」となる見通しです。しかも、ほとんど(または全て)の地域が、実際に協議会を開いて議論することなく書面のみで「不同意」を決定しました。
全自交本部に寄せられた報告では、全自交富山地連、全自交埼玉地連が、各地の地域協議会の委員として「特定地域指定に同意する」と意見し、併せて協議会の対面開催を求めました。しかし事業者の意向で不同意が大半を占めたことから「書面のみで不同意」が確定してします。
全国的に、事業者側は「コロナ禍の特殊な輸送実績が基準になっていること」を理由に、不同意を選択しています。百歩ゆずってその主張は理解するとしても、議論すらしないという姿勢は、改正タクシー適正化・活性化特別措置法の趣旨を踏みにじり、同法を形骸化する不誠実な対応にほかなりません。
特措法が目指したハイタク労働者の賃金・労働条件向上はまったく前進していません。さらにテレワーク等の新たな生活様式によって、コロナ後もタクシー需要が低迷する可能性を考えれば、まずは特定地域の指定に同意し、地域協議会で今後の適正化・活性化策を議論する必要があるはずです。
全自交本部に寄せられた報告では、全自交富山地連、全自交埼玉地連が、各地の地域協議会の委員として「特定地域指定に同意する」と意見し、併せて協議会の対面開催を求めました。しかし事業者の意向で不同意が大半を占めたことから「書面のみで不同意」が確定してします。
全国的に、事業者側は「コロナ禍の特殊な輸送実績が基準になっていること」を理由に、不同意を選択しています。百歩ゆずってその主張は理解するとしても、議論すらしないという姿勢は、改正タクシー適正化・活性化特別措置法の趣旨を踏みにじり、同法を形骸化する不誠実な対応にほかなりません。
特措法が目指したハイタク労働者の賃金・労働条件向上はまったく前進していません。さらにテレワーク等の新たな生活様式によって、コロナ後もタクシー需要が低迷する可能性を考えれば、まずは特定地域の指定に同意し、地域協議会で今後の適正化・活性化策を議論する必要があるはずです。

3月9日に行われたハイタクフォーラムの
国交省交渉
国交省交渉
国交省に対応要請
ハイタクフォーラムは3月9日に行った国土交通省との交渉で、「事業者の意向で不同意となる地域が多いことは特措法の目的に反している。所管行政として対策を」、「特定・準特定の指定基準の見直しを」といった要請を行いました。
国交省側は「特定地域については、新規参入や増車の禁止など特別の措置となるため、地域の関係者において十分に議論し、理解をえる必要がある」、「指定基準については、コロナ前、コロナ後で状況も違い、必要に応じて検討するタイミングがくれば、しっかり考えたい」と回答するにとどまり、具体的な改善策は示されませんでした。
これらの問題について、全自交新潟地連の海藤正彦書記長は「新潟交通圏では5社が営業制限に応じなかったが、運輸局は勧告も命令も出さないまま、ついに特定地域が解除されてしまった。本当に勧告・命令を出せるのか」とただしました。
また全自交北海道地連の鈴木久雄委員長は、適正車両数の基準について「札幌交通圏では46%、旭川交通圏では46・7%以上の供給削減が必要になる。(実際に)これだけの供給削減を行えば需要に応じられず、降雪時の配車は一層困難になり、雇用問題も発生する」と問題提起し、「指定基準の見直しは喫緊の課題だ」と国交省に求めています。
いま現実に、改正特措法の実効性が失われつつあり、協議会での議論すら行われない状況がある以上、まずは国交省が運用ルールを見直す以外に解決策はありません。同時に特措法の限界を乗り越えるため、タクシー事業法(仮称)の制定を求める運動を一層強化していく必要があります。
全自交はロシア・プーチンの武力侵攻に断固抗議する

平和フォーラムなどが主催した緊急街頭宣言に全自交も参加。(3月4日、新宿駅)。
連合、交運労協、平和フォーラムと連携し、抗議を行っていきます。
連合、交運労協、平和フォーラムと連携し、抗議を行っていきます。
全自交労連は、ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻に断固として抗議し、即時・無条件の撤退を要求します。ウクライナの人々、そしてロシア国内を含め世界中で戦争反対の声を上げる人々への連帯を表明します。
核兵器による脅しや原発への攻撃も絶対に許容できません。国内でも核武装論者が勢いづいていますが、核の拡散が進めば、人類を含む全生物の絶滅リスクが跳ね上がることを忘れてはなりません。
なにより、この戦争が続くほど、物価は上がり生活は苦しくなります。ウクライナの人々のため、私たち自身の平和と生活を守るため、抗議の声を。「ロシアは撤退せよ!」。
最賃違反の是正を
厚生労働省に対する要請交渉も9日に行われ、ハイタクフォーラムは小林高明大臣官房審議官に要請書を手交=写真。コロナ禍での雇用維持や感染症対策▽最低賃金法違反や労働基準法違反の摘発・指導▽累進歩合制や乗務員負担の排除▽固定給と歩合給のバランスの取れた賃金体系▽有給休暇の不適切な取り扱いの改善などを求めました。
厚労省側から踏み込んだ回答はありませんでしたが、全自交兵庫地連の成田次雄書記長は、最賃違反の常態化や、監督・指導件数が減少している事実を厳しく批判。改善を求めました。
厚労省側から踏み込んだ回答はありませんでしたが、全自交兵庫地連の成田次雄書記長は、最賃違反の常態化や、監督・指導件数が減少している事実を厳しく批判。改善を求めました。
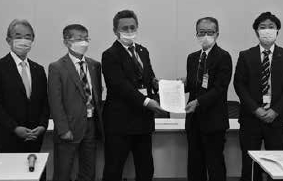

後藤委員長の下で奮闘を誓う青森地連
全自交青森地連(後藤勝委員長)は2月20日、青森市の労働福祉会館で第38回中央委員会を開催し、2022春闘方針を確立させ春闘を始動させました。新型コロナの感染拡大に配慮した縮小開催でしたが、活発な討論で闘う決意を固め合いました。
代表あいさつに立った後藤委員長は「コロナ禍で会社の経営が苦しくとも安心して働ける労働条件が必要だ。燃料や物価も上昇しており賃上げが追い付いていない。春闘で生活賃金を確保しよう」と訴えました。来賓の山名文世・八戸市議会議員は、八戸市による交通事業者への支援内容を報告。「タクシー乗務員を慰労する支援も求める。組合員となって闘おう」と呼びかけました。その後、東北地連の高橋学委員長が講演。「厳しい時こそ労働組合の出番。
賃金を改善し、協定を地域に広めよう」と述べました。
江良實書記長が春闘方針を提案し、「結果よりも経過が重要。執行部だけが会社と対等に交渉できる。要求しないものは実現しないし、協定しないものは守られない」と奮起を促し、連絡を密に取り組みを進めるよう要請しました。質疑ではLPG充填所の閉鎖や有給休暇の抑制を求める会社の言動等について対応を協議。7月の参議院選挙では「鬼木まこと」氏を推薦し全力で闘うことを確認し、最後に全員でガンバロウを三唱しました。
代表あいさつに立った後藤委員長は「コロナ禍で会社の経営が苦しくとも安心して働ける労働条件が必要だ。燃料や物価も上昇しており賃上げが追い付いていない。春闘で生活賃金を確保しよう」と訴えました。来賓の山名文世・八戸市議会議員は、八戸市による交通事業者への支援内容を報告。「タクシー乗務員を慰労する支援も求める。組合員となって闘おう」と呼びかけました。その後、東北地連の高橋学委員長が講演。「厳しい時こそ労働組合の出番。
賃金を改善し、協定を地域に広めよう」と述べました。
江良實書記長が春闘方針を提案し、「結果よりも経過が重要。執行部だけが会社と対等に交渉できる。要求しないものは実現しないし、協定しないものは守られない」と奮起を促し、連絡を密に取り組みを進めるよう要請しました。質疑ではLPG充填所の閉鎖や有給休暇の抑制を求める会社の言動等について対応を協議。7月の参議院選挙では「鬼木まこと」氏を推薦し全力で闘うことを確認し、最後に全員でガンバロウを三唱しました。

岩手地本・釜石支部の今野委員長(右端)らが、
野田市長に要請
野田市長に要請
連合岩手釜石・遠野地域協議会は2月15日、釜石市への2022年度政策制度要請を実施。同協議会の副議長として、全自交岩手地本釜石支部の今野徹委員長も同席し、野田武則市長と、市長室で意見交換しました。
野田市長は、冒頭のあいさつの中で「タクシーが苦しい状況にあることは理解しており、支援を検討したい」と発言。要請では、コロナ禍の支援について「バス、タクシーをはじめとする交通運輸、宿泊、飲食、小売り等の事業所やNPO法人等に対する釜石市独自の支援について課題を集約しながら、引き続き行うこと」などを求めました。
野田市長は、冒頭のあいさつの中で「タクシーが苦しい状況にあることは理解しており、支援を検討したい」と発言。要請では、コロナ禍の支援について「バス、タクシーをはじめとする交通運輸、宿泊、飲食、小売り等の事業所やNPO法人等に対する釜石市独自の支援について課題を集約しながら、引き続き行うこと」などを求めました。

「ハイタクの将来は賃上げにあり」とガンバロ−三唱
全自交愛媛地方本部は2月21日、愛媛地本会議室において第67回中央委員会を開催しました。主催者を代表して宮岡主委員長は「新型コロナウイルスの感染が確認されてから2年が経過したが、収束と拡大を繰り返しながら営収は低水準のままだ。会社も苦しいかもしれないが、歩合給中心の我々はもっと苦しい」と、現状を語り「ここ数年、政府が企業に対し賃上げを求めているが、国に言われるまでもなく、私たちがしっかり要求していかなければならない。
コロナ以前でも全産業労働者との格差は200万円以上ある。これを改善しなければ人は集まってこない。昨年に続きコロナ禍での春闘で厳しい状況だが、成果を上げられるよう全員で闘おう」と、訴えました。
その後、森茂書記長から活動報告と2022春闘方針(案)が提案され、月額1万円の賃上げ、一時金年間100万円を要求の柱とする2022春闘方針が決定されました。最後に、宮岡委員長の「ハイタクの将来は賃上げにある。組合員が一致団結してがんばろう」とのかけ声でガンバロー三唱し終了しました。
コロナ以前でも全産業労働者との格差は200万円以上ある。これを改善しなければ人は集まってこない。昨年に続きコロナ禍での春闘で厳しい状況だが、成果を上げられるよう全員で闘おう」と、訴えました。
その後、森茂書記長から活動報告と2022春闘方針(案)が提案され、月額1万円の賃上げ、一時金年間100万円を要求の柱とする2022春闘方針が決定されました。最後に、宮岡委員長の「ハイタクの将来は賃上げにある。組合員が一致団結してがんばろう」とのかけ声でガンバロー三唱し終了しました。
鈴木委員長「要求しなければ現状追認」
全自交北海道地連は2月14日、北海道鉄道会館で2022春闘臨時大会を開き、春闘方針を採択しました。全自交労連本部の方針を基に、労働者自主福祉運動と臨時大会時点での新型コロナ感染症拡大に伴う情勢変化を追加しています。質疑・討論では3名の代議員から補強意見があり、執行部として前向きに取り組むことが答弁されました。
鈴木久雄委員長は「新型コロナ感染症の収束の目途も立たず、私たちの産業を取り巻く環境はさらに悪化しているが、要求しないことは現状を追認していることになり、会社の業績悪化から合理化提案をしやすくする要因になる。
タクシーが真の地域公共交通として、多くの道民に認知していただくために、利用者の利便と安全・安心の移動の確保が重要だ。そのためには、運転者不足の解消が重要であり、賃金・労働条件改善が待ったなしで問われている。全自交に結集する労働組合は、生活できる賃金・労働条件確立に向け奮闘する」、「臨時大会で確立した春闘方針に基づき、各単組の組合員がおかれている現状を改善・向上させるため、全ての単組が要求書を提出し粘り強い交渉を積み重ねていただく事をお願いする」とあいさつしました。
また、7月の第26回参議院選挙で、全自交北海道地連は、比例代表選挙候補予定者として「鬼木まこと氏」の推薦を決定していることを報告し「日本維新の会や竹中平蔵を中心とする新自由主義を唱える輩は、ライドシェア合法化を目指し暗躍している。自分たちの利益のために世論受けする言葉を連ね、タクシー産業は既得権益を守るための弊害でしかないと言わんばかりの連中に、私たちは屈するわけにいかない。タクシー産業の制度政策の根幹を脅かすライドシェア合法化阻止の取り組みは、2022年も継続して取り組む」と述べました。
大会は新型コロナ感染症対策として、少人数・短時間で開催。大会議長は互信労連書記長の佐藤友彦代議員が担いました。
鈴木久雄委員長は「新型コロナ感染症の収束の目途も立たず、私たちの産業を取り巻く環境はさらに悪化しているが、要求しないことは現状を追認していることになり、会社の業績悪化から合理化提案をしやすくする要因になる。
タクシーが真の地域公共交通として、多くの道民に認知していただくために、利用者の利便と安全・安心の移動の確保が重要だ。そのためには、運転者不足の解消が重要であり、賃金・労働条件改善が待ったなしで問われている。全自交に結集する労働組合は、生活できる賃金・労働条件確立に向け奮闘する」、「臨時大会で確立した春闘方針に基づき、各単組の組合員がおかれている現状を改善・向上させるため、全ての単組が要求書を提出し粘り強い交渉を積み重ねていただく事をお願いする」とあいさつしました。
また、7月の第26回参議院選挙で、全自交北海道地連は、比例代表選挙候補予定者として「鬼木まこと氏」の推薦を決定していることを報告し「日本維新の会や竹中平蔵を中心とする新自由主義を唱える輩は、ライドシェア合法化を目指し暗躍している。自分たちの利益のために世論受けする言葉を連ね、タクシー産業は既得権益を守るための弊害でしかないと言わんばかりの連中に、私たちは屈するわけにいかない。タクシー産業の制度政策の根幹を脅かすライドシェア合法化阻止の取り組みは、2022年も継続して取り組む」と述べました。
大会は新型コロナ感染症対策として、少人数・短時間で開催。大会議長は互信労連書記長の佐藤友彦代議員が担いました。
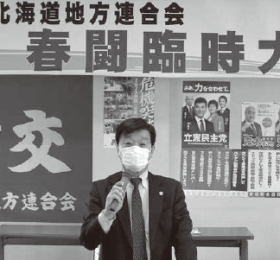
鈴木委員長は、「全ての単組が要求書を提出し、
粘り強い交渉を」と呼び掛けました
粘り強い交渉を」と呼び掛けました
結束して春闘へ
全自交富山地連(石橋剛委員長)は、2月14日、富山交通福祉棟会議室において第43回委員会を開催。執行部や加盟単組の代表委員・オブザーバーを含め15名が出席し、2022春闘方針確立に向けた協議を行い、全自交本部方針を中心に、富山地連独自の取り組みを加えた春闘方針案が満場一致で承認されました。
冒頭、石橋委員長は「賃金の大幅な減少が3年目に突入している。会社の運送収入も低下しているが、事業者に対する各自治体からの助成・給付はあっても労働者に対する補填は皆無にひとしい。今、労働者の生活維持と立て直しのための賃上げをしないと、従業員はいなくなり会社の運送収入も確保できなくなる」と、厳しい情勢下で春闘を闘う意義について強調。「2022春闘では賃金を底上げして、コロナ禍が明けた時代にきちんと働ける環境を整え、生活が回復できるようにみなさんと一緒に闘っていきたい」と述べ、2022春闘での全自交富山地連の結束を求めました。
また石橋委員長は「県内におけるコロナ感染者累計では、もはや100人に一人という計算が成り立ち、各人の周りにも感染者が出ているところまで迫ってきた。そんな中にあって、感染リスクがありながら日々業務についておられるみなさんに心から敬意を表したい」と感謝し、アルコール消毒や換気など感染防止対策について「引き続き、大変ですが、気を引き締めていただきたい」と呼び掛けました。
委員会は最後に「私たちの地域公共交通を守るため、2022春闘勝利、夏の参議院選挙必勝に向けて一致団結してガンバロー」を三唱し終了しました。
冒頭、石橋委員長は「賃金の大幅な減少が3年目に突入している。会社の運送収入も低下しているが、事業者に対する各自治体からの助成・給付はあっても労働者に対する補填は皆無にひとしい。今、労働者の生活維持と立て直しのための賃上げをしないと、従業員はいなくなり会社の運送収入も確保できなくなる」と、厳しい情勢下で春闘を闘う意義について強調。「2022春闘では賃金を底上げして、コロナ禍が明けた時代にきちんと働ける環境を整え、生活が回復できるようにみなさんと一緒に闘っていきたい」と述べ、2022春闘での全自交富山地連の結束を求めました。
また石橋委員長は「県内におけるコロナ感染者累計では、もはや100人に一人という計算が成り立ち、各人の周りにも感染者が出ているところまで迫ってきた。そんな中にあって、感染リスクがありながら日々業務についておられるみなさんに心から敬意を表したい」と感謝し、アルコール消毒や換気など感染防止対策について「引き続き、大変ですが、気を引き締めていただきたい」と呼び掛けました。
委員会は最後に「私たちの地域公共交通を守るため、2022春闘勝利、夏の参議院選挙必勝に向けて一致団結してガンバロー」を三唱し終了しました。

「賃金の底上げ」目指し、ガンバロー三唱

全自交岩手地本(森茂委員長)は2月以降、県内の大船渡、宮古、盛岡周辺、北上、花巻のタクシー乗り場で組織拡大宣伝行動を行いました。チラシを配り「夜はまったく動かない」、「最低賃金が払われない」といった悩みを丁寧に聞きました。
訂正
2月15日付1220号の2面に掲載した「春闘標語を初公募」の記事で、組合員の方のお名前が間違っておりました。「新しい資本主義の前に格差是正! 今こそ勝ち取れ2022春闘」の標語を考案されたのは林さんではなく、大和自交労組銀座支部の佐藤正三さんです。お詫びして訂正します。
全国自動車交通労働組合連合会
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-9
TEL:03-3408-0875 / FAX:03-3497-0107
E-MAIL: zenjiko-roren@zenjiko.or.jp